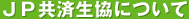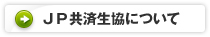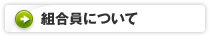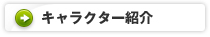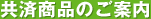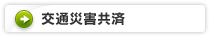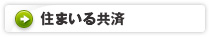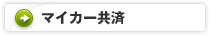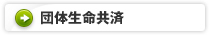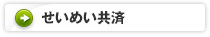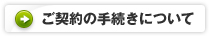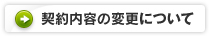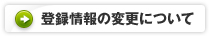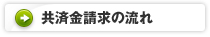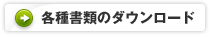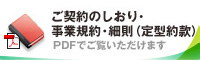新着情報
- 2014.10.14
- 御嶽山 死者数56人
長野、岐阜県境の御嶽山の噴火発生から続けられている捜索活動により、「死者56人重軽傷者69人となり、火山災害では、1991年の雲仙・普賢岳での火砕流を上回り、戦後最悪の火山被害となった」と報じた。
三十数年前に、登山のためヨーロッパに一か月間滞在した。先発隊の5人が落石により負傷し現地での入院となった。当時、家族には心配をかけまいと内緒で行ったが、ある時祖母から「酒やギャンブルはやっても登山だけはやめて」と懇願されたことを思い出した。
最近の日本列島は、広島の土砂災害(中国地方部・9/29発信)に続き、「災害列島」と云える状況にある。こうした自然災害の驚異に対し、「ひとは無力である」ことを改めて痛感する。
自然災害に限ったことではない、暮らしの中には様々なリスクがある。そうした災害や事故を、予知することは不可能だが、仲間の支え合いである「共済」を軸とした「備え」による安心を享受することは可能だ。
『備えの方策』としては「自助」「共助」「公助」がある。「公助は、法律に基づいた公的支援」、「自助(蓄え)で、全てを賄える人はそうそういない」そこで共助としての共済制度(リスク・不安⇒多くの仲間の支え合い⇒安心をシェアする)を賢く利用してもらいたい。
東日本大震災では、全国の仲間(加入者の96%)が 被災者(4%)を共済事業を通じて支援した。また、助け合いの基本である「総合共済」では、毎年4万人以上の方に共済金をお届けし、「郵政職場の仲間の喜怒哀楽」を共に分かち合う制度として、例年九州でも総合共済加入者のほぼ20%の方に対し共済金をお支払している。
今回の噴火に対し、生命保険協会に加盟の42の生命保険会社は、災害救助法が適用されたことを考慮し、被災者に保険金を全額支払うが「損保保険会社」の場合は「“天災危険補償特約〟を付けなければ保険金の支払いは出来ない、対応は正反対だ」と公表した。(10/5)
ではJP共済生協の場合の対応はどうなるのか?当然、総合共済(住宅災害共済金は除く)も大型生命共済「きずな」ともに共済金が全額支払われることとなる。
共済制度は、「多くの一人ひとりの小さな力」により、「世代を繋ぎ」、「負担公平の原則」等に基づき運営されている。JP共済生協が、将来にわたり持続的に組織共済としての「使命と役割」を果たすため「微力であっても」「無力であってはならない」ことの思いを共有していきたい。
年間で現職組合員(12年度34人13年度24人)の方が亡くなっている。9月にも若い期間雇用社員が心不全で亡くなったが、総合共済未加入者(加入手続き上の不備のため)と判明した。
支部共済担当者は、総合共済には加入していると思っていただけに、今回の事案は「二重のショックだった」、「自己責任の範疇」であるにせよ、何らかの方策もあったに違いない」と語る。
今回のような現職死亡に伴う事案はほとんどないが、その他の事由による共済金請求で「総合共済の未加入が判明する」と云う事例や事由発生後の加入によるトラブルなど、年々減少しているものの時効請求(12年度80件、13年度54件)の件数がある。
こうした状況もあり、今年度から連協を中心とした共済推進体制の確立を目指し、連協別データや実情に基づいた連協単位での「支部共済事務局長会議」を企画し、新たな共済担当者の育成にも取り組む一方で、昨年に引き続きユース・女性も含めた幅広い参加による連協別「共済サポーター研修会」を実施することとしている。
まだまだ十分な成果は得られていないが、継続した取り組みにより共済活動の裾野の広がりを確実なものとしたいと考えている。
前述のことば「微力であっても」「無力ではない」は、「核兵器の廃絶と平和な世界の実現」に向けた、高校生平和大使の訴え!! 共済活動にも通じるものを感じる。
自分流に云えば、「越えられない山はない」との思いで「一生懸命に」「しつこく」そして「諦めずに」伝えて行きたい。
11月の「東海地方部との共済交流」に、九州から重点支部とシニア・アドバイザーの方に参加を頂くが「実りある交流会」となるようにおおいに期待している。
JP共済生協 九州地方部長 江藤 定信