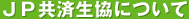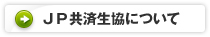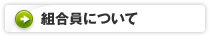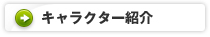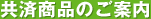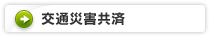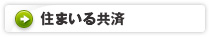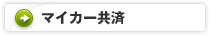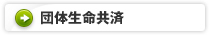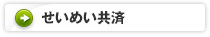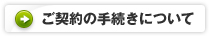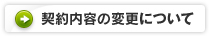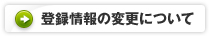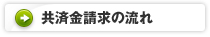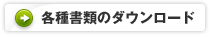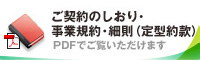新着情報
- 2014.10.06
- 章ちゃんの福祉シリーズ第一弾!「高齢化社会を生き抜く」
◆世界に類例を見ない高齢化社会
今が問題ではない。10年後からが日本社会にとって、かつて経験のない深刻な超高齢化社会に突入する。それは団塊の世代が「介護世代」に入るからである。これを「2025年問題」と呼んでいる。
介護施設が足りない、病院のベッド数が足りない、のでいる。政府によるこの春の診療報酬の改定作業が今後の政府方針を物語っている。それは「在宅医療」「在宅介護」なのである。
◆高齢化は過疎地よりも都市部に
これまで高齢化といえば過疎地(地方の代名詞)であり、限界集落という社会制度が維持できない集落への呼び名さえできた。しかしここにきて急激な高齢化は都市部とその周辺で発生することが予想されている。東京都とその周辺、千葉・埼玉・神奈川・・・、大阪・兵庫、愛知などである。日本の高度経済成長を支えた団塊の世代が最も多く居住しているからである。だからこそ都市部の病院。介護施設不足は今後深刻度を増してくる予想である。今、要支援・要介護はあわせて580万人で、地方中心に増えてきたが、今後は都市部を中心に急激に増加していくこととなる。
◆誰が介護を?子が親を看れるか?
施設や病院に入ることができるのは、要介護5などの重度の介護必要者か、民間の高額な施設に入れる金持ちか、ということとなり、普通の家庭は「在宅介護」になるのだが・・・。
日本社会は欧米と違い、三世代同居で子が親を看る伝統があった。1955年には1世帯の平均人数が5人以上であったが、2014年には2.5人(厚生労働省調べ)となり、半世紀の間に大家族制から核家族へと移行し、三世代同居は、「普通」ではなく「めずらしい」家庭となってしまった。一方、1人だけの世帯は25%を超えている。「老老介護」が急激に増加している中で、高齢者単独世帯も多くなっている。特に平均寿命の高い女性に多いのである。高齢者の7人にひとりがいわゆる「一人住まいの高齢者」である。
世帯人数から見る限り、「同居して親が子に看てもらう」時代は終わりつつあるようだ。
◆介護難民にならない為に経済的自立を
今、どのようなサービスを受けることが出るのか、どのような補助制度や補助金がでるのかを知っておく必要がある。介護施設についても、種類によって入所料金も変わるのである。サービスや補助金制度などは、行政の窓口や「地域包括センター」「社会福祉協議会」などでも教えてもらえる。
最近多いのが民間の「介護サービス付き高齢者住宅」というのが増えている。これは施設内容からサービスまで千差万別で料金もピンキリであり、内容をよく確かめなければならない。
さまざまなサービスを知った上で経済的自立が必要となる。今は定年退職年齢と年金受給年齢が異なる。親を抱えているのかどうか、配偶者の存在や収入、子供の人数、住んでいる地域、男女差など組合員の状況は組合員の数だけ違いがある。その人によって、退職後に自立できるのはどの程度なのか、それを若い世代から考え、準備しなければならない時代になったことだけは確かなようだ。
JP共済生協 四国地方部長 齋藤 章爾